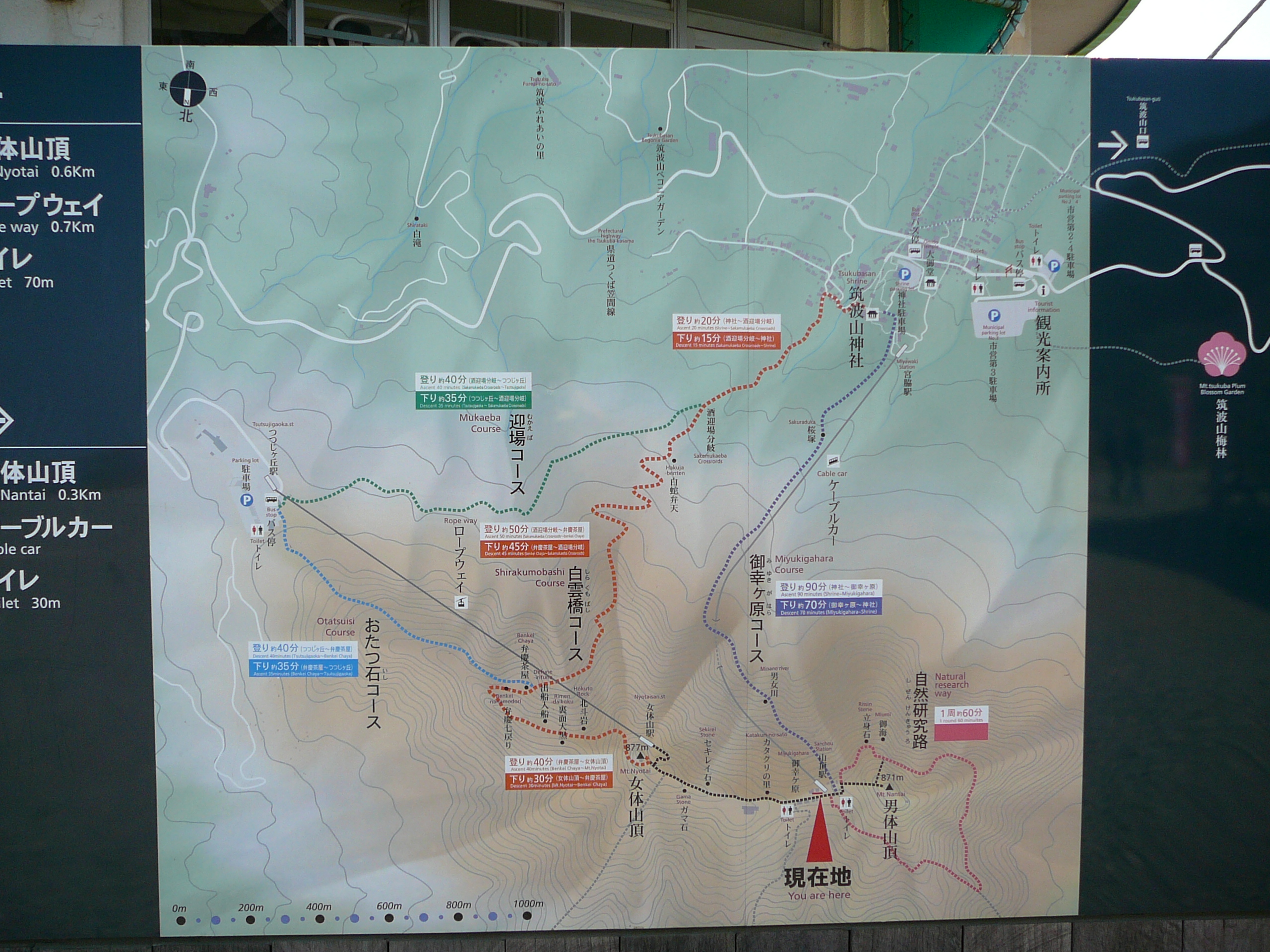 相続税
相続税 2回の相続の分け方次第で大きく変化してしまうのが相続税
人生を過ごしていると、父親の相続・母親の相続と、最低でも2度の相続を経験することになります。先に起きてしまった方を1次相続、そのあとに起きる相続を2次相続と呼びます。そして両親にまとまった財産がある場合には、1次相続の財産の分け方次第で相続...
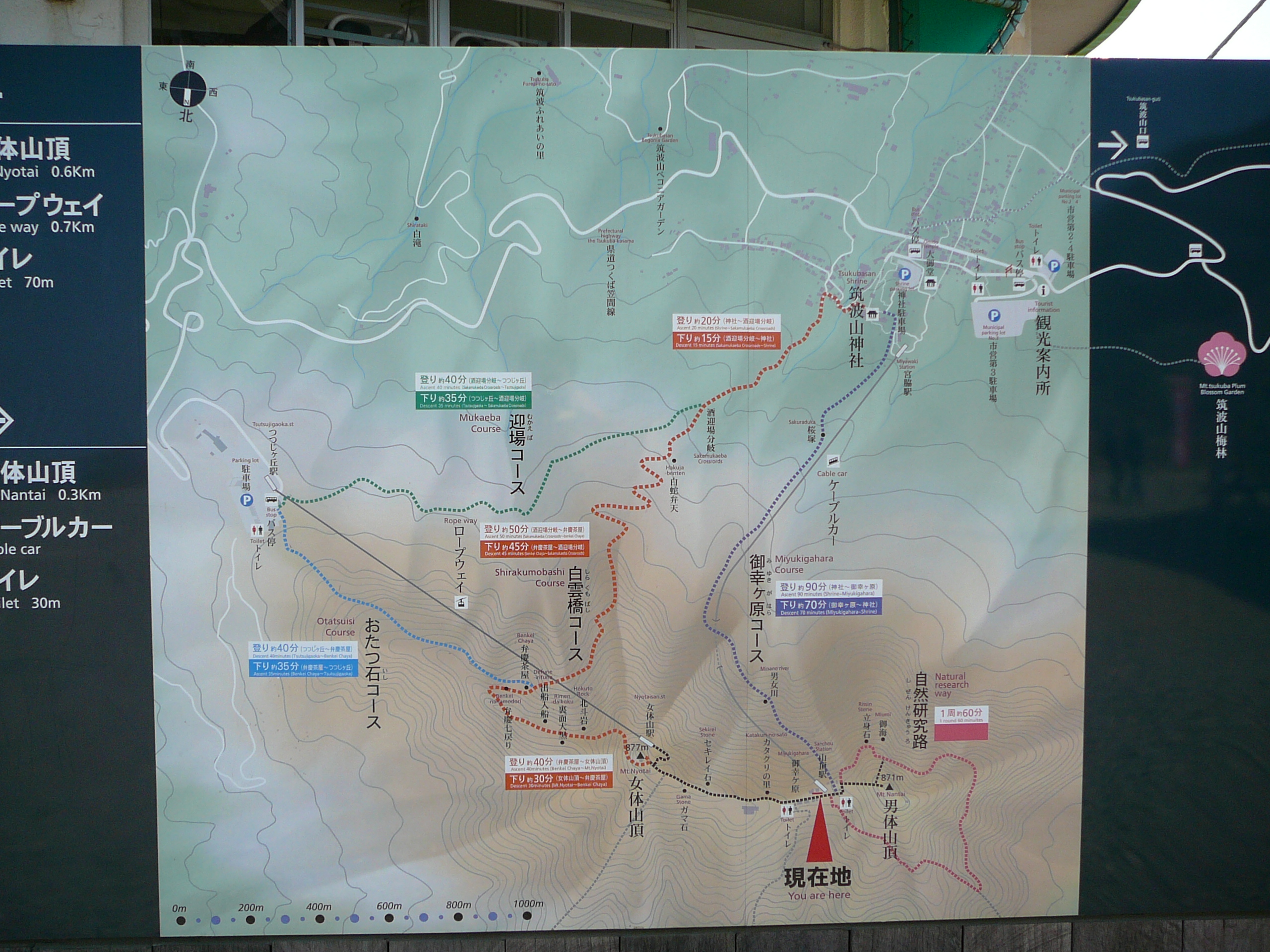 相続税
相続税 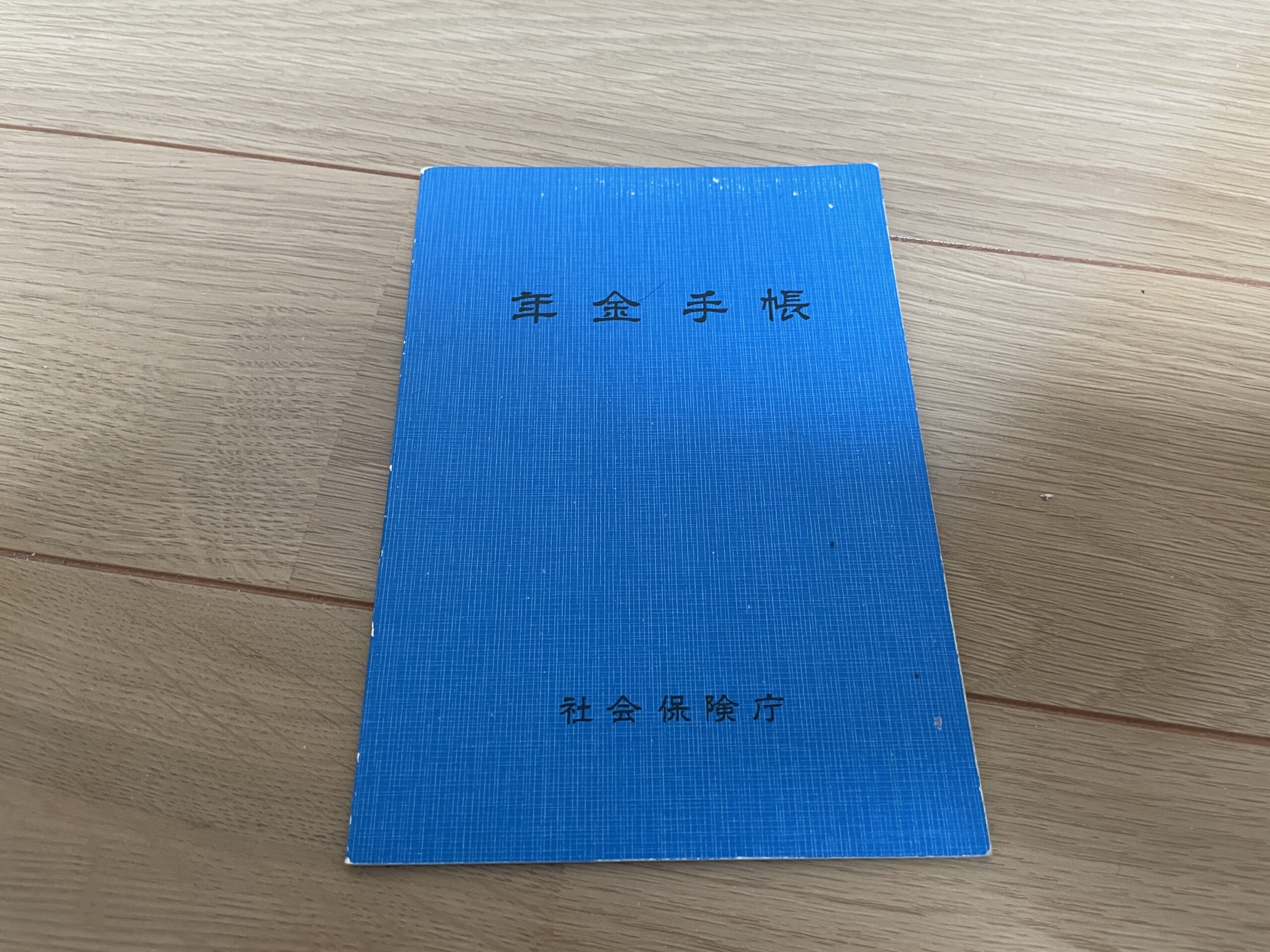 相続税
相続税 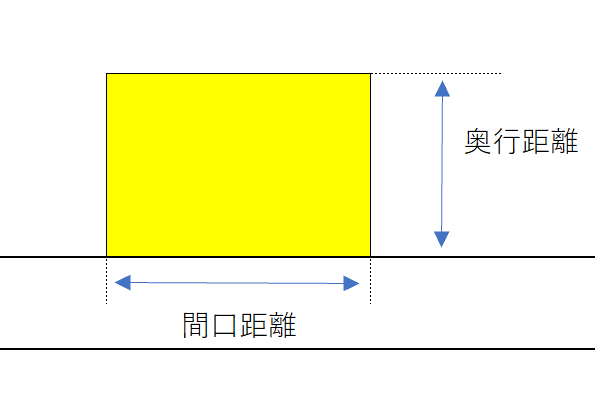 相続税
相続税  相続税
相続税  相続税
相続税  相続税
相続税 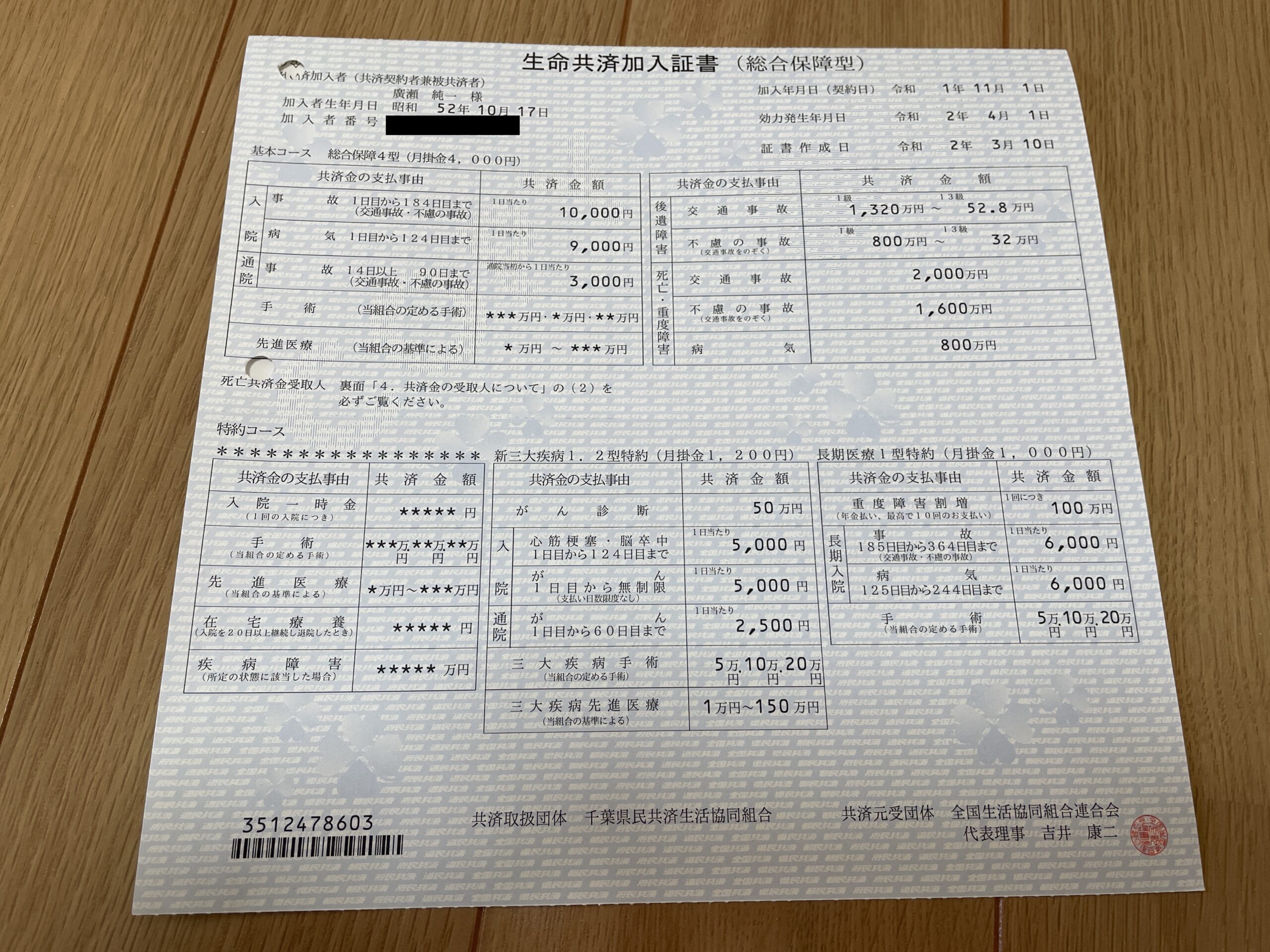 相続税
相続税  相続税
相続税 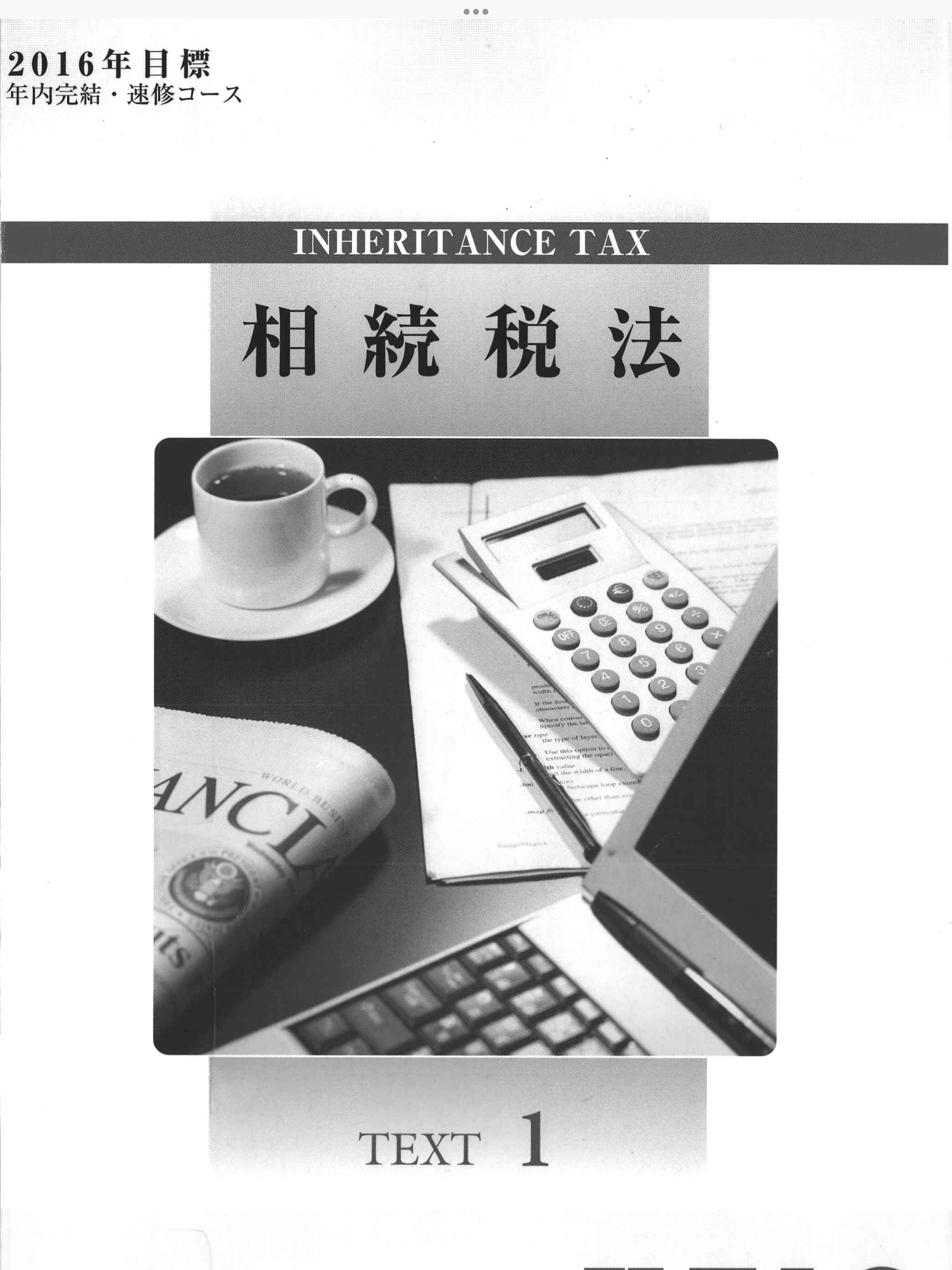 相続税
相続税  相続税
相続税  相続税
相続税  相続税
相続税  相続税
相続税  相続税
相続税 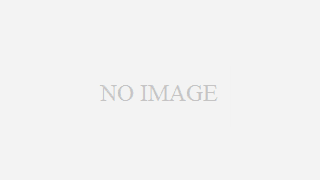 相続税
相続税  相続税
相続税 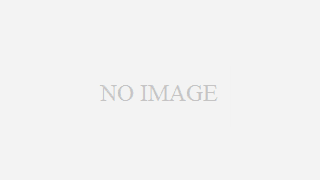 相続税
相続税 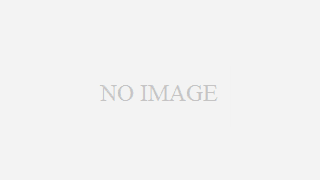 相続税
相続税