確定申告は1年分の申告をすることになりますが、準確定申告については唯一例外で1/1から年の途中までの申告をすることになります。
基本的にはどの数字であっても月割りというようなことはありません。
どこまでの期間の数字を申告すべきかまとめてみました。
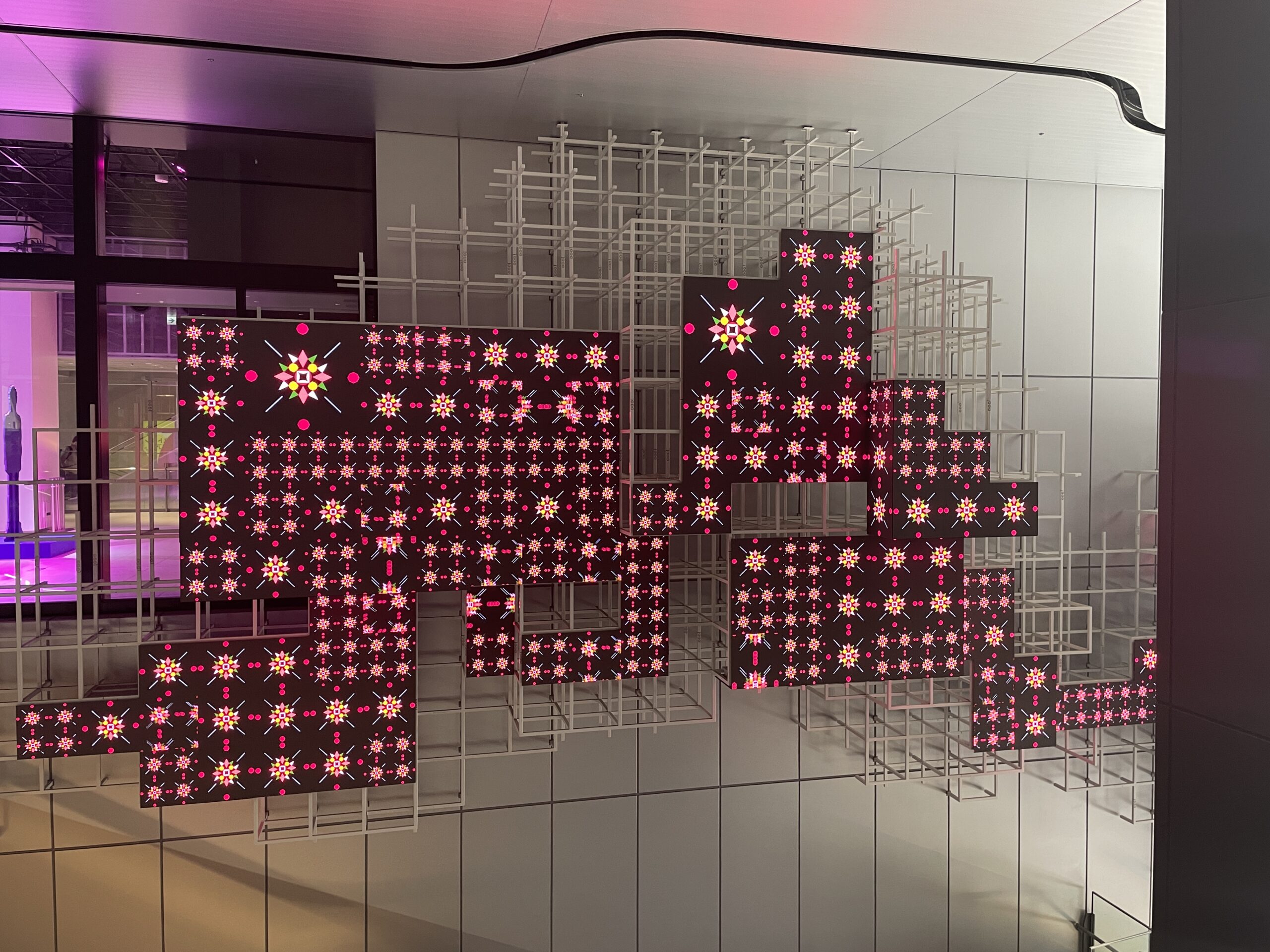
収入
収入については、1/1から亡くなった日までの収入を申告します。
ところで、亡くなった方の収入が年金だけであるならば、通常の申告のときと同様400万円以下であれば申告は必要ありません。
この400万円の金額は、月割りなど必要ありません。普段超えていた方であっても、年の途中で亡くなったがために、超えていなければ申告は必要ありません。
そのために、準確定申告が必要な方は、不動産の収入があったり、自営業者に限られてくるケースがほとんどです。
なお、青色申告している場合の特別控除額65万円(55万円、10万円)についても、そのまま引くことができます(月割はありません)。
所得控除のうち、支払いがからむもの
所得控除の中で、特別の支払いがある場合に控除できるものがあります。
社会保険料(国保、後期高齢者医療保険など)、生命保険、地震保険といったものです。
これについては、準確定申告の対象の方がご存命のときに支払ったときのものまでです。
亡くなった日が年の後半だと、控除証明書が送られてきているケースもあるかと思いますが、そこに書いてある金額を引いてはいけません。あくまで支払った分までが控除の対象です。
控除証明書がない場合には、保険会社に請求をしておきましょう。
また、医療費控除についても本人のご存命のときに支払ったものまでです。ご本人のものであっても、亡くなったあとでご家族が支払ったものは対象外です。
医療費控除については、他の論点もありますので、こちらもご参照ください。
故人様の医療費についての相続税の債務控除と準確定申告の医療費控除の関係
所得控除で、扶養などが絡むもの
所得控除の中で、家族の扶養に関するものも通常の確定申告のとおりに引くことができます。
月割の概念も一切ありませんので、通常通り引くことが可能です。
年間の収入も確定していないと思われますが、亡くなったときの見込みでOKです。
ところで、通常は同じ人が2人の方の扶養に入る事はできませんが、準確定申告の場合には、入れる場合があります。
例えば、父・母・子で生活していて、父がなくなった場合に、
父の準確定申告時に、母を対象に、配偶者控除を受けることができるとともに、
その後、子の確定申告(年末調整)時に母を対象に扶養控除を受けることも可能です。
※収入要件はそれぞれ満たしている必要はあります。
(おまけ)基礎控除などの税制改正への対応
今年は、基礎控除の金額がアップするなどの税制改正があります。ただし、12/1改正のため、現時点ではその改正後の金額を利用することができません。
そのため、以下のように対応することになっています(令和7年7月11日現在)。
提出日が12/1より前
提出日が12/1より前の場合には、従来通りのルールのため、新しい基礎控除等の数字を利用することができません。
そのため、改正前の数字で申告→12/1以降に更正の請求する
という、手順を踏むことになっています。
提出日が12/1以降かつ申告ソフト未対応の場合
12/1以降の場合には、改正後の数字を利用することが可能です。
ところが、申告ソフトがこの改正に対応していない場合があります。
この場合には、雑損控除欄に足りない部分の金額を入力して、つじつまを合わせるとともに、
どこかの欄外に、基礎控除額〇〇円と追記することになっています。
国税庁のQ&Aには基礎控除のことが書かれていますが、給与所得控除、扶養控除についても同様になるものと思われます(雑損控除で数合わせ+注記)。
<昨日の出来事>
午前中はブログとランニング7km。
午後は税理士会でした。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応

