個人事業主の場合には、会社員と違い将来のお金も自分で作らなければなりません。
いわゆる節税商品と呼ばれるものですが、こういったものにどれくらいお金をかけるべきか、まとめてみました。
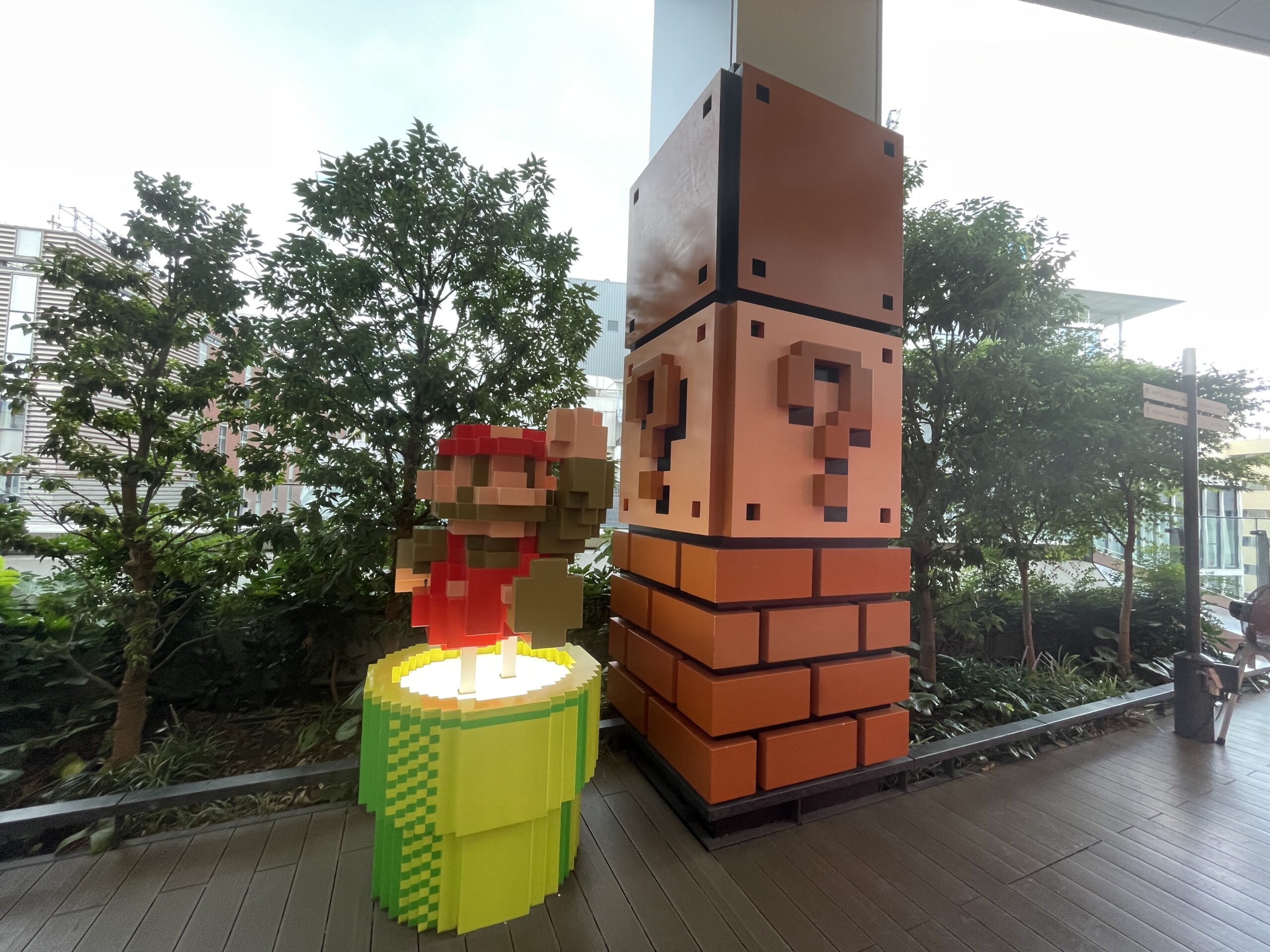
節税=お金が増える、ではない
節税のための商品として、個人事業主の場合には以下のようなものがあげられます。
・小規模企業共済掛金
・iDeCo
・国民年金基金
といったものが中心です(倒産防止共済はここでは省略します)。
ここで、節税することによって、納税額が少なくなり、結果としてお金が増えるという勘違いが非常に多いです。
これは、全くの逆でお金は減ります。
例えば、税率が30%の方が小規模共済を84万円払うと、払わなかったときと比べて25.2万円納税額が少なくなります。
ただし、お金を84万円支払っているので、58.8万円(84万円-25.2万円)お金が減ることになります。
つまり、節税すればするほどお金は減っていきます。
こういったものは、税金を減らすとこが目的ではなく、将来に向けてお金を効率よく蓄えていくものです。結果として、納税額が少なくなり、将来に向けてのお金を効率よくためることができます。
節税に関しては、こういったことを頭に入れておく必要があります。
生活ができるかどうかが大事
では、どれくらい掛金をかけるのがいいかといえば、まずご自分が生活できるだけのお金を把握して、それを差し引いてもお金が残る場合に、その余剰資金で行うべきでしょう。
発想としては、貯金と同じ考えかたは同じです。
かんたんに月30万円(納税や保険料込みで)必要なのであれば、利益が360万円あれば生活できることになります。単純に利益が400万円あるならば、40万円は手元に残る計算になります。
もちろん、あまった利益を全額ベットしてはいけません。
万が一のためにある程度お金を置いておくべきですし、まとまった支出が控えているのであればそのお金を取っておく必要もあります。それ以前に、個人事業主の場合には利益もばらつきます。
それを踏まえたうえで、金額を設定していただければと思います。
あくまで、生活できる→余裕があるから節税するという流れを忘れないようにしておきましょう。
個人の稼ぎも大事ですが、生活費の把握も大事です。
万が一の場合
個人事業主の場合には、どうしても収入が安定しないことから、こういった商品に投資していくのがつらかったりすることもあります。
こういった危機には、国民年金基金やiDeCoの場合には対応は難しくなります。
金額の減額には対応できるものの、解約してお金を払い戻すということができません。あくまで、将来受け取るためのものだからです。
これを利用してお金を借りることもできません。
一方で、小規模企業共済は金額の減額にも対応できますし、支払った掛金の何割かを借りることもできます。また、解約することでお金の払い戻しを受けることも可能です。
国民年金基金やiDeCoと比較して、途中での融通はききやすいです。もちろん、デメリットもありますが、万が一の時にも対応できるので、小規模企業共済をベースにさらに余裕があるのであれば、次に進むのがいいのではないでしょうか。
<大事なこと>
節税する場合には、余裕資金で行うべきでしょう。
節税=お金が増えるではなく、節税=将来のお金が増えるが正しいです。
<昨日の出来事>
午前にお客様との打ち合わせ、帰宅後その整理を。
午後はランニング12km、家の掃除を。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応

