 経理の基本
経理の基本 1月中にやらねばならない3つのこと
年が明けて確定申告のシーズンとなりますが、その前に提出しておかなければならないモノがあります。期限が1/31(令和8年は2/2)であるので、該当するものがある場合、早めに提出しておきましょう。※年末調整と源泉所得税の納付が年内に終わっていな...
 経理の基本
経理の基本  個人の税金【所得税・住民税】
個人の税金【所得税・住民税】  独立
独立  独立
独立  独立
独立  独立
独立  私のライフスタイル
私のライフスタイル  個人の税金【所得税・住民税】
個人の税金【所得税・住民税】  登山
登山  生前の対策・贈与
生前の対策・贈与  生前の対策・贈与
生前の対策・贈与  自分の考え・自分の事
自分の考え・自分の事  消費税・インボイス
消費税・インボイス  個人の税金【所得税・住民税】
個人の税金【所得税・住民税】  経理の基本
経理の基本 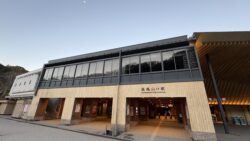 登山
登山  相続税
相続税  生前の対策・贈与
生前の対策・贈与